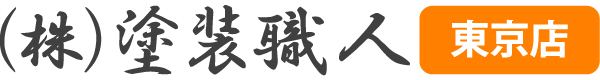大田区の施工事例のご紹介です。
築年数がかなり経っているこちらのお宅、屋根の状態があまりよくありませんでした。雨押さえがなくなり、その下の木部が露出してる状態。ここは屋根の塗替え完了後に大工が取り付け工事をします。
高圧洗浄
まずは塗装前の大事な作業、家の水洗いから開始します。
長い間メンテナンスをされていない場合は、どのお宅でも大概生えてしまう屋根のコケ。これを、最高150キロ圧で水流を放出する高圧洗浄機で、念入りに洗い落としていきます。水で足を滑らせないように、屋根の下側から徐々に上に向かって洗います。

ノズルからは勢いよく水が噴射されますが、コケは強力にこびりついていることが多いので少し水を当てたくらいでは、なかなか落ちません。スレート(屋根材)に沿って、水流を何度も往復させることで、可能な限りコケや汚れをきれいに取り除いていきます。
また、屋根だけではなく雨樋の中にも土や汚れが溜まっているので、詰まりの原因にならないように洗い流しました。このときは接続部に隙間が空いてしまっているため、水が漏れている状態。雨押さえの工事と共に、大工に入ってもらい部分的な交換をします。
付着物を落とした屋根は、色が少し残っていますが、スッキリ落とすことができました。弱っていた旧塗膜も剥がれ落ちたので、全体が白っぽくなっています。シーラーの付着もよくなり、肉厚に造膜ができそうです。






屋根の洗浄を終えたら、次は外壁へ移っていきます。こちらもしっかりジェット水流をを当てて、付着した汚れを落としていきます。軒裏や出窓も入念に。網戸の洗浄をすると汚れが落ちることで、明るさが蘇ることがあります。ただ、傷んでいる網戸に高圧の水を当てると破れてしまうため、洗浄できるかどうかはその時の状態によって変化します。
家全体の水洗いが完了したので、屋根の塗装に入ります。
鉄部のケレン・下塗り、屋根下塗り
まずは雨押さえなどの鉄部をケレンです。ケレンとはサビや汚れを落とす作業のことをいいます。ここでは、ハンドパッドというナイロンたわしで入念に研磨。
また、鉄部全体に細かな擦り傷をつけることで、下地と塗料の食い付きが向上されて、塗膜がしっかり密着してくれます。何もせずに塗装をすると、鉄部のようなつるっとした下地は塗膜が剥がれやすくなってしまうので、この研磨作業がとても重要になってきます。

雨押さえを留めているクギが抜け出ていたため、ケレンの途中に打ち直しをしています。築年数が経過しているお宅の屋根では、どうしても釘抜けが起こりやすくなります。
地震などによる家の動き、歪みなどが重なり、釘穴から徐々にクギが緩んで飛び出してくるのです。塗装をする際には、このような打ち直しもきっちりしておきます。

ケレン後は下塗りです。
今回、屋根は遮熱塗料のサーモアイを使用します。太陽の赤外線を反射することで、屋根温度の上昇を抑制する働きをしてくれます。真夏の屋根下の部屋はサウナのように暑くなることがありますが、遮熱塗料で室温も低下させることが期待できます。
下塗りはサーモアイ専用のプライマーをたっぷり塗布。
このプライマーにも遮熱性能があるので、下塗りから上塗りまでトータルで日射効果を発揮させます。塗料の性能を存分に発揮させるため、惜しみなく使用していきます。細かな部分は平バケに持ち替えて隅々まで入念に仕上げました。
庇も同様にケレンをして汚れを落としながら、研磨傷をつけました。
ここは赤錆び色のサビ止めを塗布して下塗りです。名前が表すように、サビの発生を抑制する材料を全体に塗布して、傷みやすい鉄部の耐久性を強化しました。外壁との境を塗るときは、壁に付着させないよう慎重に。小口も塗り込んで完成です。





次は再び屋根に戻り、屋根材にシーラーを塗布して下塗りします。
サーモアイ専用の白いシーラーをローラーでたっぷり行き渡らせ、屋根材を強化しながら塗料の密着性をアップさせました。このシーラーは、造膜性にも優れているので、厚みのあるきれいな塗膜に仕上げることができそうです。全面に下塗りを終えたら、この日の工程は完了となります。


次は屋根の中塗りや、養生に入ります。
外壁ツタ撤去、屋根中塗り、養生
まずは外壁に這っていたツタの根を撤去することから開始。ツタ自体は手で取りますが、根はケレンに使うナイロンたわしで擦っていきます。
取りにくいときはガスバーナーで炙って除去することもあります。ツタの根は外壁の内部に入り込んでいることがあるので、モルタルのザラザラとした壁の場合これを無理に取り除こうとすると塗装が剥がれてしまうことも。ツタの根の除去は、想像以上に手間と労力がかかる作業なのです。

続いては屋根に移動して下地処理と中塗りを行います。屋根材にクラック(ひび割れ)があったので、中塗り前に補修材をすり込んで下地処理をしました。塗料だけで対処できない所には前もって補修をして塗膜を形成していきます。
次に遮熱塗料サーモアイの主材を塗布していきます。たっぷりローラーで転がして、厚みのある塗膜に。
サーモアイの主材は、赤外線をなるべく吸収させずに透過させて、シーラーの遮熱性能を発揮させる仕組みになっています。
屋根温度上昇が抑えられ、室温も低下すれば、冷房の使用電力も抑制できますね。結果的には省エネになり、電気代の節約に貢献する塗装と言えるのではないでしょうか。




仕上がった屋根は、陽の光を浴びてとても艶やかな光沢が輝いています。惜しみなく塗料を重ねているからでしょうね。下屋根も同様に仕上げています。屋根の施工後は外壁の塗替えに入る前に、塗装しない部分の養生を行いました。
手すりの笠木部分には滑りにくいノンスリップマスカーでくるんでテープで固定しています。ここはベランダに出入りするときに足を乗せることもあるため、滑りにくく養生する必要があるのです。
窓はマスカーでぴったり覆って、風で煽られたりしないようにしています。養生は塗料の付着を防ぐだけでなく、塗り分けの線出しの意味もあるのでテープは真っ直ぐに、そして剥がれないように留めています。


雨樋にはミッチャクロンというプライマーを塗布して、塗料の密着力を強化しました。透明な材料なので、塗り落し箇所がないかしっかり確認しながらムラのないように仕上げていきます。

塗りムラがあると密着度の差が出てしまうという以外に、上からたっぷり塗料を重ねても下塗りのムラが出てきてしまい見栄えがよくないのです。そのため、まんべんなく塗布して仕上げていきました。
雨樋中塗り、外壁下塗り
引き続き、雨樋の中塗りから開始。前回、ミッチャクロンを塗布して塗料の食い付きを向上させたので、この日はシリコン塗料を重ねて中塗りしていきます。
最近、雨樋や雨戸は、飛散の少ないマイクロファイバー繊維の4インチローラーで塗装することが多くなってきました。それでも、細部は塗りにくいですから刷毛で仕上げていきます。雨樋の連なった部分に刷毛でしっかり塗料を乗せて塗膜をつけます。
外壁との間のせまい隙間にはベンダーという道具を使用しました。こちらはヘラの片面にパイル織の布がついているタイプなので、壁には塗料を付着させずに雨樋の裏面だけを塗装することができます。場所によって道具を持ち替え、手早くきれいに厚膜をつけて仕上げていきました。


次に玄関ドアや出窓の養生です。ドアは塗装工事中でも頻繁に使用する場所ですから、開閉できるようにビニールで覆っています。
このビニールはガムテープと一体になったマスカーと呼ばれるもの。ドアの取っ手や鍵穴部分は露出させ、使用できるように施しました。出窓もマスカーで包んでテープでぴったり留めておきます。中塗りをした雨樋も養生をして外壁塗装の際に、塗料が付着しないように。

外壁の下塗りへ。シーラーを塗布して下地と塗料の密着度を向上させていきました。全面にまんべんなく塗布することで、塗料の密着度を強化して、長持ちする塗装に仕上げていきます。

外壁は屋根などに比べ、塗膜が剥がれることは多くはありませんが、まれに以前の業者が下塗りをしっかり行っていなかったのでは?と推測される事例に出会うことがあります。塗装工事のどの工程にも意味がありますから、ひとつひとつ丁寧に、段階を追って塗装の耐久性を上げることが必要です。
外壁補修、下塗り、中塗り
次に下塗りした外壁のクラック補修です。
モルタル外壁は水分が蒸発される過程や、家の歪みなどの構造的な要因などにより、クラック(ひび割れ)が起こりやすい壁と言えます。そのため、発生したひび割れはこの段階でしっかり補修してから塗替えを行い、クラックの再発を抑制させます。
クラック部分に微弾性のパーフェクトフィラーを小さなローラーで塗り込んでいきます。この材料はクラックに柔軟に対応するので、ひび割れを再発させにくくします。



クラック補修後、修復した部分も含めて全体をパーフェクトフィラーで下塗りをしました。たっぷり塗り重ねることで、塗膜の厚みが確保でき、肉厚に仕上げることができます。
午後からは水性シリコンセラUVという塗料で中塗りを開始します。色はアイボリーのため、下塗りの白との違いが少しわかりにくいかもしれません。ベランダ内壁は室外機をずらして、裏側もしっかり塗装して塗膜をつけていきます。
下の写真は、中塗りが完了した外壁部分です。ベージュがかっていた壁が、すっきりとアイボリー色に塗り替えられました。惜しみなく塗料を重ねているので、モルタルの凸凹した肌が少し丸みを帯びているように感じます。


次はさらに上塗りを重ねるので、より厚みが付加されて耐久性の高い塗装になっていきます。
外壁塗装、屋根上塗り
サーモアイによる遮熱塗装の屋根上塗りです。先回、中塗りまで完了させているので、もう一度塗料を重ねて肉厚な塗膜をつけ、遮熱性能が存分に発揮される塗装に仕上げていきます。
まずは、ローラーの入りにくい部分をハケで塗り込んでいきます。専門用語で「ダメ込み」と呼ばれるこの工程で、塗り落しや掠れを防ぎ、全体に均等に塗膜が形成されるようにします。細部が仕上がっていると、全体を塗るときにもスムーズに進めることができます。目地バケを使用して鉄部と屋根材の間のわずかな隙間に塗料を付着させていきました。



こちらは場所を移動して下屋根を塗る曽根カズ。雨戸塗装で「ハケ目を出さずに塗るのが得意」と自負するだけあり、下屋根の鉄部もツヤツヤと平滑に仕上げています。外壁との見切り線もまっすぐに出すことができ、とてもきれいですね。
下屋根の次は、また大屋根に移動しました。ダメ込みを終えた曽根がローラーで全体に塗料を重ねて厚みのある塗膜に仕上げていきます。ローラーは縦横に転がしてムラなく行き渡らせました。




一方、外壁では塗装指導員でもある星野が、細部を塗り込んでいます。窓枠周りは養生をしていますが、ローラーでは塗りにくいのでコシのある刷毛で、窪みに下塗りのフィラーを乗せていきました。柔らかい刷毛だと奥や隅まで届きにくいことがあるので、硬めのものできっちり塗り込んでいます。
雨樋の裏に当たる面は、ベンダーという塗装道具で塗布しました。小さなローラーも入らず、刷毛でも塗りにくい場所は、柄に敷布がついたこの道具がぴったりです。敷布は両面付いているものもありますが、今回は壁のみ塗装したいので、片面タイプを使用しています。雨樋は養生をしていますが、必用以上に付着させることなく済むのでとても便利な道具です。
細部の次は、外壁全体の上塗りを進めました。ローラーに含ませたシリコン塗料をたっぷりと重ね、中塗りまでにつけた塗膜により厚みを付け足していきます。凸凹とした外壁ですが、惜しみなく重ねられた塗料により、丸みを帯びたような状態に仕上がりました。
屋根縁切り、雨押さえ取り付けと雨樋上塗り
次に屋根の縁切りに移ります。縁切りとは、屋根材同士の重なりが塗料で詰まっている部分を、マイナスドライバーやカッターなどで隙間を空けていくことです。
屋根材同士がくっついた状態だと、わずかな隙間から入り込んだ水が毛細管現象によって吸い上げられ、雨漏りなどの要因に繋がることが考えられます。これを防ぐために縁切りをするのですが、屋根塗装をしたら絶対行うというわけではありません。はじめての屋根塗装に限った場合、塗装をしても隙間が埋まることはあまりないからです。
ただ、こちらのお宅のようにサーモアイや、キルコートといった特に厚膜に仕上がる塗料を使用した場合や、屋根の傾斜があまりないお宅は縁切りをしましょう。そうは言っても、はじめての塗替えでも縁切りをしないと不安…というお客さまには行っていますのでご相談ください。
今回、縁切りはマイナスドライバーを屋根材の間に差し込み、そのまま持ち上げるようにしながら隙間を作っていきました。その時々により、カッターや皮スキ(金ベラ)を使うこともあります。
一方で板金技能士の内田は、屋根雨押さえ(棟押さえ)の取り付け工事を行いました。こちらのお宅では、雨押さえがなくなっており、その内側の木部が露出している状態だったのです。
まず、既存の木部を撤去して新しいものに交換。その上から新たに雨押さえを設置して修復しました。これで雨漏りもしっかり防ぐことが可能になったと思います。




雨樋は接続部に隙間ができており、水が漏れてしまっていたので部分的な交換工事をしました。

中塗りまで終えた雨樋に上塗りをしていきます。仕上げ塗装は、飛散のしにくいローラーで行いました。塗料の含みもよく、ハケ目が出ないので平滑な塗装面に仕上げることができます。中塗りでつけた塗膜にさらに厚みを出しながら、つややか塗り上げていきました。
上塗りの完了した横樋は、とてもきれいな光沢が出ていますね。交換工事をしたところも、他と同様に下塗り中塗りと塗装していきます。
エアコンホースカバーは白い塗料で塗替えです。刷毛に塗料をたっぷり含ませ、軽快に動かしながら塗膜をしっかりつけていきました。




塗装工事、雨戸と屋根の鉄部塗装
次に雨戸や、取り付けた新しい雨押さえなど、鉄部の塗替えを進めていきます。
雨戸は塗りやすいように、窓枠から外して立てかけて施工しています。先ずはケレンから開始。汚れや錆を削り落しながら、下地全体に細かな傷をつけていきました。塗布面がツルツルとしていると、塗料がしっかり引っ掛かる面がないため、あえて擦り傷をつけることで食い付きをよくしています。
塗り替えをしても、すぐに剥がれてしまっては意味がありませんので、剥がれにくく長持ちする塗装にするため入念に研磨していきます。
ケレンに使う道具はさまざまあり、サビや弱った塗膜は皮スキという金ベラで削り落すことが多いです。下地が平面であれば、ディスクサンダーという電動工具を使用することも。微細な傷をつける際は、ナイロンたわしやサンドペーパーを使用しています。
ケレンが完了後、雨戸の四隅にマスキングテープを貼って養生です。枠の部分は塗装しないので、塗料が付着しないようにカバーします。また、塗り分けの線をきれいに出す目的もあるので、真っ直ぐに貼って剥がれてこないように手でよく押さえておきます。
下塗りは茶色いサビ止めを塗布し、サビが再び発生することを抑制。耐久性も向上させました。中塗りはチョコレート色のシリコン塗料を塗布して、厚みのある塗膜を形成していきます。雨戸塗装は刷毛で行うことが多かったのですが、塗料をよく含み、飛散の少ないローラーを見つけて以降はローラー塗装も多くなりました。ハケ目も出ないので、フラットに仕上げられます。

まずは、雨戸の端や段の窪みになっているところを塗り込んでから、全体に塗料を乗せていきます。ローラーは縦横に転がして、厚みがムラにならないように均等に仕上げました。
乾燥後、さらに上塗りを重ねて、より塗膜の厚みを出しながら艶やかに塗装。外壁が塗替えられてきれいになると、付帯部分が目立つようになります。家全体の美観をアップさせるためにも、付帯部分の仕上げも入念に行っています。養生をはがしてしっかり乾燥させたあとは、元の場所にはめ込んで完了です。美しい光沢のある塗り上がりになりました。


雨戸塗装の次は、屋根鉄部の塗装です。先回、新しく取り付けた雨押さえを同様にケレンし、サビ止めで下塗り。屋根と同じく、遮熱塗料のサーモアイをたっぷり塗布して塗膜をつけていきます。細かな所は刷毛を使用し、塗布した跡を出さないように平滑に、光沢を出しながら仕上げていきました。


下屋根トタン部塗装、遮熱塗料で省エネ
こちらの現場での塗装工事も、残すところあとわずかとなりました。今回は下屋根のトタン部を仕上げて屋根塗装を完了させます。サーモアイの下塗り材を塗布した部分に、中塗り材を重ねていきます。
トタン部はフラットに仕上げるため、毛足の短いローラーを使用して、ハケ目を出さないように塗装。塗布した面が、鏡面のようにツヤツヤとした光沢が輝くように塗料を重ねています。天窓部分に塗料が付着していますが、マスカーできっちり養生をして固定しているので、心配はありません。

思い切った作業を可能にし、作業効率をアップさせるためにも、養生を丁寧に行うことは欠かせないのです。外壁との境界は養生ができないので、真っ直ぐきれいに仕上げるのは職人の腕の見せ所でもあります。
遮熱塗料のサーモアイは、上塗り材で反射できなかった赤外線を吸収させずに、透過させることで下塗り材の遮熱性能を存分に発揮させます。下塗り~上塗りのトータルで日射反射率をアップ。
屋根温度の上昇が抑えられると、屋根下の室内温度が低くなり、ひいては冷房器具の使用も抑えられるのでエコですね。これからの暑くなる季節にはもってこいの塗料と言えると思います。
中塗り完了後は上塗りを重ね、より塗膜の厚みをつけながら、耐久性を高めて完成となりました。


門塀、外壁下塗り
次に1階の外壁と門塀の塗装に入ります。
門塀にはたくさんのツタがびっしりと這っていたので、まずはこれらを取除く工程からスタート。
手で葉っぱとツタを剥がしていき、残ったツタの根はガスバーナーで炙っていきます。ツタの根が外壁の内部に入り込んでいる場合は、無理やりに引っ張ろうとすると、塗膜や下地を痛めてしまう恐れがあるので、バーナーの火で焼き取ります。
それから、ワイヤーブラシやナイロンたわしといった、ケレン作業に使う道具で丁寧に擦り落していきました。門塀や外壁の周りには植木やウッドデッキなどがあるので、塗料が付着しないように周囲を養生します。




植木は布シートを被せてテープで固定。ウッドデッキや雨樋にはマスカー(テープ付きビニール)を敷いたり、包んで塗料が付着しないようにしました。



養生が完了後、外壁にシーラーで下塗りをしていきます。下地と塗料の密着力を向上させ、剥がれにくい塗膜をつける下準備です。ローラーで染み込ませるようにたっぷり塗布しました。
また、シーラーには下地を強化させる働きもあるので、傷みや荒れた塗装面を落ち着かせて固めます。吸込みのある壁も、ここで吸込み止めをしておくことで、主材の塗りムラを防いで均等な厚みの塗膜に仕上げることができます。


次にフィラーを使用して2回目の下塗りをしていきます。この材料は微弾性なので、クラック(ひび割れ)に追従し、柔軟に対応してくれます。ひび割れが発生しやすいモルタル外壁に適した下塗り材と言えます。
フィラーはぼってりとした材料のため、肉厚な塗膜が形成可能。ただ、その分塗るときにも力を要しますが、塗りにくいからといって薄めすぎてはいけません。材料の持つ性能が低減されてしまうからです。
下塗り材でも上塗り材でも、性能を十分に発揮させるためには希釈を適切に行い、惜しみなく塗布することが重要になります。門塀も同様にフィラーで下塗りし、肉厚な塗膜を形成する準備をしました。

外壁・門塀の下塗りと中塗り
外壁や門塀の下塗りを進めていきます。
写真は少し見えにくいのですが、パイプ・ホース類の密集している外壁を塗装しています。ローラーが入りづらい部分なので、小さめの刷毛で細部までしっかり材料を塗布。使用しているパーフェクトフィラーはクラックに柔軟に対応しますし、肉厚な塗膜が形成できる材料です。
室外機や、お隣との境界には布シートをかけて塗料が付着することを防いでいます。気をつけていてもローラーの遠心力で塗料はあちこちに飛散することがあるため、養生は念入りに行います。


門塀の道路側は中塗りを開始。濃厚なシリコン塗料をローラーで塗布し、均一な塗膜に仕上がるように行き渡らせていきました。白系の色ですが、下塗りとは色味が少し違うので塗っている部分が分かりやすいですね。掠れや塗り落しのないように確認しながら塗り進めます。
こちらは住宅側の門塀を下塗りしています。端にはラティスがあり、狭くなっているので小さなローラーで隅からフィラーを塗布。場所に応じて道具を替え、より効率よく、きれいに塗膜がつけられるように塗装します。


次はいよいよ最終工程の外壁・門塀、付帯部です。どのように仕上がるのか楽しみです。
外壁・門塀、雨樋上塗り
最終工程です。中塗りを終えた門塀にさらに塗料を重ねて上塗りをしていきます。
塗っている所は明るい白色で、少し粘着感のある状態になっています。塗りやすいよいうに希釈しすぎてしまうと、このような濃厚な塗料にはならないのです。適切に希釈した塗料を惜しみなく使用して、家を長期間保護してくれる耐久性の高い塗膜に仕上げていきました。
門塀は土間との境界部分を刷毛で丁寧に仕上げていきます。ラインがガタガタしていると見栄えがよろしくないので、まっすぐな塗り分け線になるように塗装。テープで養生をしてあるので、はみ出しを心配せずに進められました。
そして、雨樋の仕上げ。外壁に面しているところは塗料が付着してしまっているので、そこも補修しながら塗膜を全面につけていきます。塗料の含みがよいローラーを使用しているので、ハケ目を出さずに艶やかに仕上げることがきました。




塗り替えが完了したお宅の外観です。外壁は白くスッキリとしており、陽に当たってツヤツヤとした光沢で輝いています。門塀もきれいになり、新築に近いような状態に蘇ったのではないかと思います。